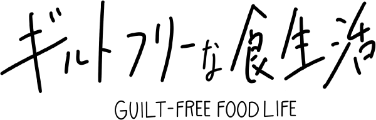FOOD AND LIFE食と生活

地球にも優しいギルトフリーな食生活で、ソーシャルグッドな選択を
- 2025.08.20
- 食と生活

ギルトフリーな食生活というと、低カロリー・低脂質など「体に優しい」健康志向を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし実はギルトフリーには、「地球に優しい」という視点も含まれています。今回は、すぐにでも始められる「地球に優しいギルトフリーな食生活」のヒントをお届けします。
自分の体だけでなく、地球にも優しい。これからのギルトフリー

もともとギルトフリーの発祥は、2010年代にオーストラリアで生まれた「砂糖なし・添加物なし・グルテンフリー」のお菓子「グリスボール」とされています。そこからギルトフリーの言葉が浸透するにつれ、ギルトフリーが対象とする範囲も健康や美容から広がりを見せています。
近年ではSDGsやサステナビリティへの関心の高まりに合わせて、「罪悪感」の視点を「自身の健康や生活」から、「地球環境」に広げる動きが生まれています。特に海外では、動物愛護や生産者の労働環境、環境保全の観点から見たギルトフリーへの意識の高さが特徴的。日本でも徐々に、社会貢献につながる“ソーシャルグッド”なギルトフリー食品へのニーズが増えつつあります。
カロリーや添加物に配慮するだけでなく、食べることを通じて社会貢献ができると、普段の食事がもっとポジティブで豊かな体験になります。自分や家族の身体だけでなく地球にも優しい選択ができる、ギルトフリーな食生活のポイントを紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
日々の食事で「食品ロス削減」を実践する

日本の食品ロスは年間約472万トン(農林水産省・環境省令和4年度推計)にものぼります。食品ロスは単にもったいないだけでなく、食べられずに捨てられてしまう食料の製造や輸送、廃棄処分によって余分なCO2が排出されるという点で、環境にも大きな影響を及ぼしています。
年間の食品ロスのうち、約半数が家庭から出たとされるもの。普段から食品ロスの削減を意識して行動することは、私たちができるギルトフリーな食生活の第一歩といえるでしょう。食品ロス削減の工夫には、具体的に以下のようなものが考えられます。
- 冷蔵庫の在庫管理をして食材を使い切る
- 余った食材はアレンジして再利用する
- 食べきれなかった食材は冷凍保存する
- 外食の際には食べ切れる分だけ注文する
- スーパーや通販で賞味期限間近商品や規格外商品を選ぶ
「規格外商品」とは、本来なら市場に出さない規格外の野菜を活用した商品のことです。また味や品質には問題がないのに廃棄される食品を、価値ある商品としてアップサイクル(再活用)する取り組みも注目されています。
地産地消で、環境にも地域にも優しく

地域で採れた食材を地域で消費する「地産地消」は、環境にも地域経済にも貢献できるギルトフリーな取り組みの1つです。「地域の直売所やマルシェで野菜や果物を買う」「地域ブランドの加工品を選ぶ」といったように、取り組むハードルが低いのもポイントです。
地産地消の環境面における大きなメリットは、フードマイレージ(食材の輸送にかかる環境負荷を数値化したもの)を低減できること。生産地から食卓までの輸送距離が短くなるために、CO2排出を抑えることができます。
地域経済への貢献の面では、地元食材を購入することで地域の生産者を支えられるというメリットがあります。地域の農業や漁業の振興は、食料自給率の向上にも直結します。また地産地消には他にも「新鮮な食材を入手できる」「生産者の顔が見えることで食の安全につながる」といった多くのメリットがあります。
“エシカル消費”を意識した選択を
エシカル消費とは、環境や人権、動物福祉に配慮した商品・サービスを選ぶ行動のこと。日本でも認知度が上がっており、実践する人も増えています。食事シーンにエシカル消費を取り入れることで、「食べることがそのまま社会貢献になる」、そんなギルトフリーな食生活を叶えることができます。
ただしエシカル消費で注意すべきは、サプライチェーンの過程で矛盾が生じている可能性があることです。例えば植物由来の素材にこだわった商品でも、実際には海外の劣悪な労働環境で生産されているかもしれません。言葉だけの“エシカル消費”にしないためにも、原料調達から生産、消費、廃棄までのあらゆる過程が透明化された「トレーサビリティ」のある商品選びも重要となっています。
それらのことを踏まえた上で、ここでは食におけるさまざまなエシカル消費の例を紹介します。
フェアトレード商品

フェアトレードとは、発展途上国の生産者に適正な対価を支払う貿易の仕組みのこと。フェアトレード原料が使用された食品を選ぶことは、貧困の解消や労働力の搾取を防止につながるギルトフリーな取り組みの1つといえます。
オーガニック認証の食品

化学肥料や農薬を使用しないオーガニック食品は、生産過程における食品土壌や水質汚染、生態系破壊などの環境負荷を軽減できる点がメリットです。また食の安全の観点から、身体にも優しい選択といえるでしょう。
「オーガニック」や「有機」を商品名に付けられるのは、国の基準に基づく認証を受けたものだけです。認証を受けた商品には必ず「有機JAS認証」がついているため、それを目印にするとより安心な食品選びができるのではないでしょうか。
植物由来の代替肉やヴィーガン食品

ヴィーガンやベジタリアンなどの動物由来の食品を避けるライフスタイルは、動物愛護の観点だけでなく、畜産による環境負荷の低減という観点からもメリットがあります。
近年では著名人でヴィーガンを取り入れる人が増えており、大豆ミートや植物性ミルクなど商品種類も増加中。ベジタリアンやヴィーガンにもさまざまな種類があるため、自身の価値観やライフスタイルに合わせて選択すると良いでしょう。
規格外商品・アップサイクル食品

食品ロスのところで既に触れた規格外商品とアップサイクル商品は、食品ロス削減だけでなく生産者の収益向上につながるのも魅力です。スーパーや産直市場などでも購入できますが、規格外野菜に特化した販売サービスもあるため、気軽に入手可能できるのもポイントです。
またアップサイクル商品は、単に規格外野菜の活用をするだけでなく、農業支援などの付加価値をつけた商品開発がなされている例も少なくありません。アップサイクル商品を選ぶ際は、商品そのものだけでなく開発プロジェクトの背景を合わせて調べてみるのもおすすめです。
再生可能なバイオ素材を使用したパッケージ

食品そのものだけでなく、サステナブルなパッケージ素材を使用した商品を選ぶのもエシカル消費の1つです。主なサステナブルパッケージの例は以下の通りです。
▼サステナブルなパッケージの例
- バイオマスプラスチック:
とうもろこしやサトウキビなどの再生可能なバイオマス資源を原料とするプラスチック - 生分解性プラスチック:
微生物により水とCO2に分解されるプラスチック - バンブー素材:
焼却時のCO2が少なく、再生力に優れた竹の繊維からできている素材
まとめ
「おいしく食べること」「健康を守ること」、そして「地球に優しい選択をすること」。そのすべてを同時に叶えられるのが、“ギルトフリーな食生活”です。自分の身体のことだけでなく、誰かや何かを思う優しい行動の積み重ねが未来につながっていきます。
地元の野菜を選ぶ、残り物をアレンジして使い切る、フェアトレードのチョコレートを買う。ギルトフリーな食生活の実践のために、ちょっとした取り組みから始めてみてはいかがでしょうか。