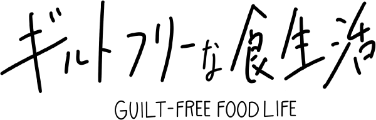FOOD AND LIFE食と生活

家庭でできる、子どもの心身を育む「食育」の実践
- 2025.04.30
- 食と生活

私たちが生きていく上で欠かせない食事。栄養面はもちろんのこと、誰かと楽しく食事をする経験は、心の健康にも大きく影響します。そんな「食」に関する正しい知識を身につけ、生涯にわたる健全な食生活を実践していくために重要なのが「食育」です。
食育は全年代にとって必要なものですが、特に幼少期から食育を推進することは、将来にわたる食習慣の基礎をつくる上で大きな役割を果たします。近年では保育園・幼稚園や学校での給食の時間に食育を実践するケースも増えていますが、子どもが初めて食事をし、長い時間を過ごす家庭での食育は子どもの成長にとって特に重要です。
とはいえ一口に「食育」といっても「何から取り組めば良いんだろう…?」と不安に思われる方もいるはず。そこで今回は子どもが食育を学ぶメリット、そして家庭で子どもと一緒にできる食育の取り組みを紹介します。
「食育」とは?
今ではすっかり認知されている「食育」という言葉。2005年に制定された「食育基本法」によると「食育」は以下の通り定義されています。
・生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの
農林水産省「食育」とは
・さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することできる人間を育てること
私たちは食べることなしに生きることはできません。つまり食育を学ぶということは、すべての基礎となる“生きる力”を育てることを意味するのです。
また上の定義からもわかる通り、食育とは知識を習得することだけを指すのではありません。食に関する正しい知識を身につけ、「実践」していくことこそが食育の意義であるといえます。
「食育」の具体的な取り組み
「食育」というと「栄養バランスの取れた食事」など、健康面にフォーカスした取り組みをイメージする人が多いのではないでしょうか。しかし健康面はもちろんのこと、地産地消や食の安全・安心、食品ロスの低減に関する取り組みなど、非常に多岐にわたります。
国では食育の取り組みをわかりやすく発信するため、普遍的な重点項目を12個の「食育ピクトグラム」にまとめています。

1〜7までは主に個人の健康や生活に関する取り組みとなっています。
8以降は個人的なことにとどまらず、私たちの食の背景にある自然や生産者の営み、食文化に関する取り組みとなっています。食育は、これらの食に関する取り組みを包括的に網羅しているのが特徴です。
幼少期から食育を学ぶメリット
ここでは、子どもが食育を学ぶことによる主なメリットを紹介します。
学力・体力の向上につながる

食習慣は子どもたちの健全な成長と密接に関係しています。実際に文部科学省の調査によると、朝食をしっかり食べる子どもほど子どもの学力や体力が高いという結果が出ています。
子どもの持つ力を高めていく上で、幼少期から栄養バランスの取れた食事を3食しっかり食べる習慣を定着させていくことが大切です。
食事の楽しさ、食のありがたみを実感できる

食育の学びは子どもの体の成長だけでなく、心の健康や成長にもメリットをもたらします。
例えば食育では皆で食卓を囲んだり、一緒に食事をつくったりと、食事の楽しさを学びます。その中で子どもたちは心の健康につながる愛情や信頼感などを育んでいくことができるでしょう。
また豊かな食を生み出す自然の恵みや、命をいただくこと、生産者や食事をつくる人の取り組みなどを学ぶことは、子どもの心の成長にもつながります。食のありがたみを実感して感謝の心を育むことで、食べ残しの軽減も期待できます。
望ましい食習慣の定着

幼少期は将来にわたる食習慣の基礎をつくる時期です。この時期に食育を実践することで、子どもの中に自然と望ましい食習慣のサイクルが定着していくことができます。
ただし、子どもの年齢が上がるにつれて、朝ごはんを食べずに学校に行ったり、ときには友達とジャンクフードを食べたりと、ライフスタイルも食習慣も変化していくもの。将来的に子ども自身で食生活をマネジメントできる力を養っていくことを意識し、年齢に応じた食育のアプローチ方法を変えていく工夫も必要です。
食事のマナーや社会性が身につく

食事中の会話や、食事の準備の際のコミュニケーションの中で、子どもが他者と協調する力を身につけることができます。さらに正しい食事マナーの実践を通じて将来にも役立つ社会性を育めるのも食育のメリットです。
子どもにとって、家庭にとっての「食育」
ここまで、子どもにとっての食育の大切さを解説してきました。
しかしいくら家庭で正しい食育を実践していたとしても、ただ食事を“提供”しているだけになってしまっているためにその重要性を子どもが理解できていない、という例も少なくありません。そうなると、成長した子どもが自ら望ましい食習慣を実践していくことはなかなか難しいでしょう。
もちろん幼い内から食育のメリットや重要性をすべて理解することはできません。あまり小難しくならないよう、「元気に遊ぶために朝ごはんを食べようね!」など、まずは子どもにもわかりやすい表現で食育のメリットを伝えていきましょう。
また日々忙しく家事に育児に奮闘する中で「家庭での食育を完璧に!」と考えるとプレッシャーになってしまうかもしれません。食事は子どもの心身の健康を育んでいくものでもありますが、同時に「家族で食卓を囲む」という大切な思い出をつくるものでもあります。親子にとって窮屈な食卓にならないよう、まずは家族で食事を楽しむことを前提に自分なりの食育の形を探していくことが重要です。
家庭で簡単に実践できる食育の例
ここでは気軽に家庭に取り入れられる食育の例を紹介していきます。
子どもと一緒に食事の準備をする

子どもが自ら食育を意識し、実践できる力を身につけていくためには、まず食に対する興味・関心を高めることが大切です。そのため家庭において子どもが主体的に食事に関わる体験を積極的につくるようにしましょう。
例えば一緒にスーパーに買い物する、献立を考えてもらう、料理のお手伝いをしてもらうなどが考えられます。料理に関しては、子どもの年齢によってどこまで手伝ってもらえるかが変わってきます。まずは一緒に野菜を洗うなど簡単なことからはじめましょう。野菜を洗うことは水遊びの要素もあるため、年齢が低い子どもも楽しめるはずです。
徐々にステップアップしていき、子どもに達成感を味わってもらうのもポイント。子どもに「料理って楽しい!」と思ってもらえれば、さらに食に対する興味・関心が高まるはずです。
食事中のコミュニケーションを心がける

食卓は、家庭での大切なコミュニケーションの場です。まずは家族で一緒に食事をするだけでも、家庭でできる立派な食育といえるでしょう。コミュニケーションをとりながら食事の楽しさを伝えていくことが食育の第一歩です。
また食卓は食事マナーや正しい配膳、日本の伝統的な食文化の継承など、子どもにとって学びの場でもあります。楽しい雰囲気の中で覚えた知識は身につきやすいもの。一緒に楽しく食事をしながら、食にまつわる知識を伝えていきましょう。
育てる・収穫する・食べるのサイクルを体験させる

子どもが食の大切さを実感できるよう、野菜を育てる体験や農業体験をするのも効果的な食育の取り組みの1つです。1から育てて収穫し、食べるところまでの一連の流れを体験することで、普段何気なく食べている食への感謝の気持ちを育むことができます。種子から育てて、成長を見守り、収穫する過程を通じ、もともと嫌いだった野菜を克服したという例も聞かれます。
外で行われている農業体験に参加させるのも良いですが、日常的に野菜を育てて収穫する体験をさせるのであれば、簡単にできるプランター栽培などの家庭菜園がおすすめ。シソやバジルなど簡単に育てられるものからはじめるのも良いでしょう。
まとめ

家庭での子どもの食事は離乳食からはじまって幼児食に移行していきます。そのためどうしても「親が正しい食事を用意し、子どもに与える」という意識になりがちです。子ども自らが食に興味を持ち、主体的に実践していけるよう、食育の大切さを日頃からしっかりと伝えていきましょう。
何より食育の根底には、「食事を楽しむ」ことがあります。家族で一緒に食事を楽しむことを大切に、家庭の食育の一歩を踏み出してみてください。